割れ鍋にとじぶたログ
2008年〜2010年頃まで
「千鳥足」の新さんとやっていた
お絵かき掲示板のログです。
PCに保存していた分だけ、UPです…!
ご感想などありがとうございました。
お兄さんと1・2・3
扉が閉まる。綱吉は時計を見上げた。獄寺たちが戻るまで、一時間か。リボーンが帰ってくるのもその頃。リング守護者の会合までまだ随分と時間がある。
机に置いたままの雑誌が目についた。
暇つぶしになるかと、開いてみればショックを受けた。
(!! や、山本ってば何読んでんだよ〜! ヒトの家で!)
彼は素知らぬ顔で読んでいたので、表紙はアイドルグラビアでも漫画か専門誌かと思っていた。まあでも山本らしいといえばらしい。
(うわ〜。こ、こんなの読むんだ)
フツウの健全な中学生って……、と、新鮮な気持ちがした。自分は棚上げである。わざわざローアングルでヒップを写したり、ビーチバレーをして飛び跳ねたりしている。海はハワイか。鮮やかに青い。
なぜかビキニパンツを引っぱって砂を入れるそぶりをする一枚があったが、ビキニの紐をズラして魅せる日焼け肌と白肌とのコントラストに綱吉はドキリとした。
(ど、どしぇー、きわどっ。すっごいなぁ)
眼が釘付けになった。
と、
「?」
奇妙な焦燥感に襲われる。唐突だった。
「っ?! な、なに? 骸も見るの?」
「そうさせていただきましょうかね」
ポンと、綱吉の肩を叩くと同時に左側から顔をだしたのは六道骸だった。
制服姿。彼はつい先ほどやってきた。部屋の隅に座り込んだまま、獄寺たちとの歓談に加わることもなくジッとしていた筈だが。
綱吉は混乱した。ひどく跋が悪い。
「きょ、興味あったの? こういうの」
「そりゃあ僕だってオトコのコですからね」
「あ、そ、そお。ふーん」
沈黙。肩に置かれた手がなれなれしいとか、親しげに口をきく仲でもあるまいにとか、色々と思う筈が綱吉の頭は回らなくなっていた。
「どうしたんです? 早くめくってくださいよ」
「あっ? う、うんっ」
「あんまり読み慣れてる感じしませんね」
「だ、だってこれは山本が持ってきたから……だよ」
「くふふ。知ってますよ。見てましたから」
からかい混じりに言って、骸は「ああ」と喉をしならせた。紙面に人差し指を押しつけて、ショートカットの少女を示す。
「こういう子、好みじゃないですか?」
「あ……。きょ、京子ちゃんに似てる?」
「彼女より乳がデカいですけどね。好みですか?」
「なっ。そ、そんなことないけどっ」
「ほう。僕はこっちのがマシだと思いますけどね。めくりますよ」
「つ、つうか、べつに似てればいいとかっ、そういうんじゃないし」
慌てつつも、綱吉はぶつぶつ呻く。骸のオッドアイが横合いから注がれているのをひっきりなしに感じた。
(なっっ、なんでさっきからッ、ずっと見てるんだよ〜。やりにくいなぁ!)
余計に混乱して、綱吉は頬を紅潮させる。
骸は不思議そうに尋ねた。
「そーゆーんじゃないですか? オカズなんて」
「お、オカッ……」
一瞬、絶句する。
「も……っ、な、なに言ってんだよ。そういうつもりで読んでんじゃないんだぞ」
「じゃあ何故?」
「ひっ、ヒマだし、時間あるし」
気後れした喋り口に、骸はクスッとした。
見下した微笑で、腹が立ってもおかしくない筈だが、この状況下では蠱惑的に思えて綱吉は困惑する。六道骸ってオレより年上だった、と、今更ながらに思い知った。
「興味もあるし……? やっぱり予想通りに初心ですね。沢田綱吉。使い方、教えてあげましょうか?」
「は、はあ? お断りだから!」
強気になろうと、綱吉は声を張り上げる。
彼のペースに呑まれたらとんでもないコトが起こると予感が胸を掻き回している。
「君と僕の仲ですよ。ほーら、君だってずいぶんと体温と心拍数があがってきてるじゃないですか」
「や、やめろよっ……」
骸の左手が綱吉の胸をまさぐった。
首もと、地肌にピタリと指が吸着する。骸が笑みを深めた。
「汗もでてる。興奮状態ですね」
「馬鹿なこと言うな。ちょ、くっつくなよ」
オッドアイに凝視されている。恐ろしくなって綱吉はふり向きもできない。全身が硬直する。息もつまる。
「怖がらないでくださいよ。君の体の準備ができてるか確認してあげただけですから」
「じゅ、準備ってナニ!」
「いい具合のようですね。それじゃあ次ですけど、そうですね……臨場感を出した方が楽しめますかね?」
「う、うわっ。おい……、骸っ! こんなのいやらしいだろっ」
「だから楽しいんでしょうよ」
左手で綱吉の左手を掴んで、骸が、無理矢理にグラビアアイドルの胸に綱吉の手のひらを押しつけた。
ぐりぐりとひねるような動きも与える。
「女の人の胸って、やわらかいですよ」
「……ひっ……!!」
綱吉は頭をパンクさせかけていた。
「その様子じゃ触ったことないんですね。母親のは? イメージできるでしょう? あと肌も滑らかで、心地良いんですよ……。クセになるくらいに」
綱吉の手を握り直して、器用にも人差し指をつまむ。
つつつと、ヒップラインを撫でさせられた。
(ひ〜〜い〜〜〜〜っっ!!!)
「イメージしてくださいね……。触られている感じは、こうですよ」
「ぎゃあ!」
肩にあった筈の手がいつの間にやら後ろにあって綱吉のヒップを上に撫で上げた。言いようのない気持ち悪さで綱吉は鳥肌をたてる。
(お。おかしい。何だこれは何じゃあああ!)
抗議を眼に込めて、思わずふり返ると、オッドアイと衝突した。間近にあるので迫力がすごい。相手が綱吉を凝視していた分、綱吉もそれを知っていた分、ぎらついて見えて心臓を鷲掴みにされた。
文句を言おうとしたのに、声を弱々しくしてしまう綱吉だった。
「や……、あの……、もういいから。撫でないでください」
「ぷっ。君、痴漢されたらそんなこと言うんですか?」
「え?! そ、そんな」
(痴漢されないよ! ええええ?!)
「呑気ですよねぇ……」
「う、うわっ」
双丘の片方に狙いをつけてさわさわされると背筋が粟立った。血の気がザーッと音をたてて引く。ひとしきり撫でた後で骸は綱吉の腰を掴んだ。
「ほら手が止まってますよ。僕がページを選んであげましょうか?」
「〜〜〜〜っっ! お、おまっ! オレから離れろ!」
「何故? まだ何も教えていないも同然ですよ。楽しいですねえ」
「ぜ、全然楽しくないぃ〜〜っっ!!」
絶叫した時、骸が手を止めた。これはイイですね、とか言って自分の指先でグラビアを撫でる。下着姿のグラマラスな女性が、眉を寄せて、ガーターベルトを穿いている最中だ。
「どこがいいかわかりますか?」
「えぇえええ? も、もういいよっ」
「君、乳の谷間ばっか見てますよ」
「放っておけ! もうめくる!」
「待ってください。ここですよ。恥ずかしがっているのがイイ」
言いつつ、中指のツメ先で女性の表情を指し示した。
綱吉は明確に恐怖を感じた。自分は身の置き場に困って居たたまれないのに、恥ずかしがって赤面してるっていうのに、そんなことがイイとか言い出すヤツが隣にいる。
口がぱくぱくとした。オッドアイからの視線がまさしく綱吉に突き刺さる。
わざと言っているのだろうが、骸は何事もなかったかのように澄ました顔をするから余計に対処に困った。
「あ、あうっ……」
「裸体はないんですかこれ?」
(山本ォ、獄寺くん! リボーン!! お兄さんヒバリさん母さんランボイーピンなんでもいいから早く帰ってこぉい!!)
「おや。眼が泳いでますよ」
「だあああっ?!」
フッと耳に息をかけられて動揺する。
綱吉も限界だ。叫んだ。
「オレ、ゲームするから! 読むのやめるから!!」
「クフフフフフフフフフ。まだ教えてあげられること、いっぱいありますよ?」
「もういい! もういらん! 誰がいるかぁあああ!!」
「おや、暴れますか? 落ち着いてくださいよ」
丁度、その頃、沢田家の玄関に沢田奈々が立っていた。
両手に買い物袋を提げている。上の階から響いてくるドタバタ音に対して、しみじみとした調子で呟いた。
「男の子って元気でいいわねえ」
綱吉の悲鳴も、奈々は気にしなかった。
おわり
居酒屋で
げらげらした笑い声が酒屋の天井にとどく。ボンゴレファミリー親睦会と名がついてはいるが実質はお祭り騒ぎのための口実だ。
「まあ僕に女性経験を聞くなら打ちのめされることを覚悟してもらいましょうか」
六道骸はニヤニヤしながら、机に肘をついて山本武をねめつける。
「まあモテそうな顔してるもんな」
「クフフ。どうでしょうね。君もモテるでしょうけど、経験は僕が勝っていると絶対に……」
「ふーん」
骸の後ろに、そそそ、と、沢田綱吉がにじりよる。
顔は真っ赤で、トロンとした声を出した。
「骸ってけいけんほーふなんだぁ」
「きましたね、酔っぱらいが……」
小さく呟いて、骸はコップを手にした。黄色いビールが入っている。
「なんだよ。じゃまか?」
「席替えくらい好きにしていいでしょうよ」
少し戸惑い気味に返しつつ、しかし次の瞬間に骸はギョッとしてオッドアイを見開かせた。
ビールを一口、含もうとしたところで視界に影がよぎった。ふり返りかけて、事態はもう避けられないレベルに差し迫ると悟る――、反射的に頭を引き戻した、急だったので少しだけ。
その瞬間に綱吉がちゅうとキスをした。
頬にあたったやわらかな感触に、骸は息を止める。
「!!?」
(なっ――、ん、ですか、これ、え?)

綱吉はキスするための顔をする。眼を閉じて唇を少し突き出して、骸の耳に触れそうな場所に頬を押しつけて、ふうふうしながら喋った。
「けいけん、ひとつ追加ぁー」
「なっ……、つ、ついか」
オウム返しにしか出来ない。骸の動揺は大きい。
完全に酔っぱらっていて、前後もわかっていないという態度で、綱吉は骸の肩にしなだれかかった。
「骸って体温ひくいなあ。気持ちいい」
「酔ってますよ沢田くん……」
唖然として呻きつつ、骸はまだ眼を丸めている。
一呼吸置いて、心臓がばくばく動いた。
(き、キスされた。ほっぺたにキス)
そして咄嗟の反射神経で避けてしまわなければクチに。キスされるところだった。
事実に愕然として、骸はまじまじと綱吉を観察した。
(してもいいのか? 僕と?)
それってどういう意味だ、と、思考が絡まってほつれる。
と、視線を感じて骸は目線を持ち上げた。
沢田綱吉はついには骸の腰に抱きついて「ふあーねむーいぃいい」とかぼそぼそ呻く。
六道骸は、山本武の沈黙に気まずくなった。
「ぼ、僕は、迷惑なんですけどね」
なんとか骸は声を絞りだす。
「ふーん……。まあ、ツナはけっこーお前のこと気に入ってるかんなぁ。つうか絡みぐせあんだよな、酒入ると。スマンな」
頬を引っ掻きつつ、山本。はあとか返しつつ骸は複雑だった。
なんだ、いつもこうなのか……。とか、なんでおまえが謝るんだ……。とか、
すきま風を胸に感じる。しかしあえて無視して、六道骸は話をつづけることにした。冷や汗が額ににじんでいる。
「それで、ええっと、オンナの……こと……でしたっけ?」
「むくろおー」
「な、なんですか」
「オレ男だよ?」
綱吉は骸に抱きついたままで夢見心地だ。
言葉につまった。骸はあいまいにうなずく。
「知ってますよ。君ね。あんまりべたべたしないでくれますか」
「だってぇえ、骸っていつもガードかたいからぁあ。酔ってる今じゃないとだめかぁと思って」
「ぼ、僕は君ほど酔ってませんよ……」
山本武がモノ言いたげな眼をしているのに気付いた。
見返すと、彼はポツリとうめく。
「確かにお前、経験ホーフだな。男性経験もできたな」
「あははははは、山本、うまいこという!」
どこがだこのやろうども、と、内心で思いつつも骸は愛想笑いを浮かべた。色々と衝撃的で、ダメージが深くて、それ以外にやり過ごす方法が浮かばない。
後々に、目撃者は山本武くらいだという事実に骸は安堵した。
(よ、よかった。なんとかごまかせそうな人間だけに見られて……)
(にしても沢田綱吉……。やはり危険だ)
親睦会は深夜に解散した。黒曜中の仲間と帰りつつも、骸は夜道に嘆息をこぼす。
眉間をしわ寄せて唇の感触を思いだそうとしてみた。
うまくいかなかった。……唇に触れてみる。避けたのはもったいなかったのかもしれない。
おわり
泣かないで、今は笑って
地下室のライトは数が少なく光量も低い。
床に分散しているかたまりが闇に紛れたが、
(ちがう違う違うぅう! オレ、こんなことのために十代目になろうって思ったんじゃない! 知らねえよこんな世界っっ、おれ、こ、こんな……!!!)
「ひっっ、えぐっ、えっ、ぁっ、あっ、あ!」
泣きじゃくる綱吉の横を最初に通りすぎたのは恭弥だった。
隼人は、階段の一段目で立ち止まる。
「十代目……」
武が、ため息混じりに隼人の肩をたたいた。
一言、二言と耳打ちされて隼人は悔しげに視線を俯かせる。
綱吉に敬礼をしてから階段を駆けあがった。了平はすれ違いざまにうめく。
「沢田。こういうのはオレも苦手だが。極限で生きる者同士、ぶつかれば、片方が潰れることもある」
「キツすぎねえか?」
「これでいい」
武とリボーンが低い声で話している。
階段の上の方から聞こえてきた。
「…………!!」
綱吉は、階段を少し昇っただけのところで、血の海を前に立ち尽くしていた。涙があふれる度に喉が張り裂けた。綱吉は声を殺して喚く。
ちゃぷん、と、眼前の赤い水たまりが揺れた。六道骸が血の上に立っている。
彼の黒い衣装が血を吸ってさらに黒く染まっていた。綱吉は骸の眼差しに恐怖した。綱吉を見上げるオッドアイは清らかに澄んで見えて人殺しの目に思えなかった。他の皆だってそうだ。
(オレ――、どう、すればっっ)
喉が痙攣を起こした。綱吉は全身に浴びた返り血を隠すべく無意識に体を縮めていた。
血まみれになった両手をにわかに握りこんで自らの胸に寄せる。
「あっ……、ああ……。えっ、えあっ」
がらがらと崩壊していくのが、とても大事なもので、綱吉は自分が取り返しのつかない道を選んだと思い知る。
自分の体も手も臭い。血で臭い。綱吉の涙は止まらなかった。
「ボンゴレ」
涼しげな声。吐息が額にかかった。

骸は綱吉の前で足を止めていた。深くしわが寄った眉間に触れるか触れないかの距離に唇を置いている。
「少しだけ、教えてあげましょう」
ぴんと、手袋を嵌めた左指が立てられた。
「ひとつ、手に血がつくとなかなかにおいが消えませんから手袋をすること。ひとつ、忘れようという努力はしないこと。ひとつ、後悔はしてもいいですが泣きはしないこと」
額の真ん中に生暖かなものが触れる。
六道骸の唇の感触。
綱吉は鳥肌をたてて震えた。人のぬくもりが恐ろしかった。
「…………っ?! や、な、なにぃ」
「スキだらけですよ。今の君は」
「そ……な……っ」
喉をしゃくりあげつつ、綱吉はゆるく首を振った。
「こういうときは、笑えばいいんですよ。笑えてくるでしょ? この状況」
「そなっ、む、無理ぃっ」
(そんなこと言われたって、たって、ひとが大勢――、死んだのに――……。オレが邪魔だって言ったせいでっ。こ、こんな、こんなことになるなんて思わなくって!!)
「っ、ぐっ、うっ、ううっ! ひっ」
「最後のひとつ。泣き虫はドンになれませんよ?」
綱吉はごしごしと涙を拭う。
「ひっく、ひッ、っ、うああああ」
「君の決断がこうやって世界を変えていくんです……。いい勉強になりましたね。ほら、ボンゴレ十代目? こんなにも簡単に思い通りになるなんて、笑えるでしょう」
「うわっ、ああああ! あああああ!!!」
泣きじゃくる綱吉の額に幾度となくキスをして骸が己の体温を伝える。綱吉には慰めにも思えたし侮蔑を込めたからかいにも思える。血肉ある人間が同じ人間を殺すのだと骸の体温が教え込もうとする。
「やだぁあああ、こんなのいやだぁあああっっ」
「…………」
骸は笑みを深めた。
微かに唇を離して、綱吉の額に息を吹きかけながら、歌うように囁く。
「本気で死にたくなったらいつでも僕が殺してあげますからね」
「ううっ、うっ、ああ、ああんっ、あーっ! ああぁっ……!!」
綱吉は慟哭を深めた。階段を昇った誰かが扉を閉めたのか血のにおいが渦になって充満する。室内にも脳髄にも。頭がおかしくなりそうだった。
おわり
××

「おや? 来客のようですよ、××」
黒い世界に足を踏み入れてから、自分以外の人間を初めて見つけた。
パジャマ姿の沢田綱吉は破顔して駆け寄った。
「六道骸!」
「こんにちは。沢田綱吉」
「よかった、今困ってるんだよ」
綱吉は肩を弾ませて暗くよどんだ周囲の闇を見渡す。
「ここ、どこかわかるか? 一体、何がどうなってるのかちんぷんかんぷんで……。何かわかるなら教えて欲しいんですけど」
六道骸はクスクスと口角をつり上げる。
綱吉は眉を寄せた。六道骸の姿をした人間はふたり。勝ち気な表情をした制服姿の骸。寡黙に無表情なジャケット姿の骸。
挨拶をしたのは勝ち気な方の六道骸だ。彼は、指先でもう一人の六道骸につけた首輪を弄ぶ。
「かわいい僕の骸……。ずいぶん、沢田綱吉にこころを許してしまったんですね。もうこんなところまで入ってきてますよ」
言いながら、人差し指の腹で喉仏をぷつりと押した。硬さを愉しむようにコリコリと指を動かされても片方の骸は静寂を保つ。骸は問いかける。
「気持ちいいんですか? こおんなに深いところまで他人を銜え込むのっていやらしいですよ……。望んでそうするなんて僕にはわかりませんねえ」
「む、骸? 六道骸だよな」
「ええ。六道骸ですよ」
「どっちが?」
「両方ともがです。僕とこの子が一つでいるときの精神状態が六道骸です」
「お前……、二重人格みたいになってたの?」
「そういう解釈が楽かもしれませんが、違いますね。同一人物です……しかしこの人は僕の始祖であり父であり母であり兄であり弟であり子孫でもある。意味がわかりますか?」
「ぜ……ぜんぜん」
「つまりは、同一ですが、魂は違うということ」
「????」
「クフフフフフフ……。沢田綱吉。君を気に入っていますが、すべてはあげられませんね。この子も僕も。だめですよ。浮気をするなんて」
骸の目は片方の己を見下ろす。
「…………」
彼は無感情に骸を見上げていた。その眸は両方ともが赤い。勝ち気な方の骸は、両目が青く澄んでいた。
「骸……。ぼくは欲しい。あの子とキスしたい」
「お父さん、だめですってば。赦しません。君も綱吉も僕のものだ」
話が理解できず、放心していたが自分の名前がでてきて綱吉は正気になった。
すると、この場面の異常性がよくわかる。
(に、逃げなきゃ)
本能で悟って、後ずさる。
「これ、お前の精神世界?」
「違いますね。ここは魂の融合地点です。精神なんて容易いワードではカバーしきれない」
「お前、もっと簡単にしゃべれ!」
イライラして、綱吉は叫んだ。
赤目の骸は、鼻筋を骸に舐め取られながらも右目だけを動かした。綱吉は赤目に見据えられてドキリとする。
「君は欲しい……。でも逃げろ」
「えっ?」
「混ざるとキケンだ」
「お父さん、アドヴァイスは不要ですよ。彼には。ボンゴレ十代目なら逃げられるはず」
「な、何いってんだよぉお前らはっ」
「走れ」
「骸……。仕方ないですね」
青目の骸は、そっと赤目の彼の唇をふさいだ。
ギョッとして目を剥いて、綱吉は悲鳴をあげた。六道骸同士のラブシーンに驚いたのだが同時に胸に吹くのはすきま風。動揺したとは、わかるが、
「なぁっ……?!」
自分の両手足が透けてきている。周囲の闇に同化しつつあった。
「ん……。くふふ、いたければいいですよ? 僕はね。観客があった方が燃えますから」
青目の彼が赤目の己を抱いている。互いの顔を押しつけあう姿は慰めあうようにも見える。
「――――っっ」
先の忠言通り、とにかく、走りだそうと意を固めたが、綱吉は肩越しにふり返る。本能的な呼びかけだった。
「じゃあな! また来るから!」
「…………」
「…………」
少年の小さな体は闇を振り切るべく闇に飛び込んだ。すぐにかき消える。二人の骸はやがて外の世界に綱吉の存在を感じた。
しばらくの沈黙。辺りは完全な闇が支配して無に戻る。
「惚れるだろ?」
赤目の彼が言った。青目の彼は、骸の後頭部を両手で掴んで固定すると額に口づける。
「××、…………」
ぼそぼそした声でささやく。
骸の赤い目が光る。彼は、頷きながら微笑んだ。
「×△……、そうだな。次の招待状はぼくが作ってあげましょう」
おわり
あおぞらおとし

シィンと空気が凍る。誰もが息をとめて瞬きをとめて向かい合わせに重なった少年二人を凝視した。
獄寺隼人の知っていた内容はこうだ。
『十代目は骸のヤツを説得した。リングを捨てて、やすっちぃ犯罪者に戻ろうとするヤツに慈悲をかけた。ボンゴレファミリーに戻っても大丈夫だって伝えてくるよと笑って手をふった』
あるいは山本武の知っていた内容はこうだ。
『ツナは骸が死のうとしてるってわかってたから止めに行った。いざとなれば自分の命を盾にしてでも止めると言っていた。ツナは、これは最終手段だけど、そうすれば骸は死ぬのをやめると複雑そうに呟いた』
そしてリボーンの知っていた内容はごくごく単純だった。
『骸はツナを愛していた。ツナも骸を愛していた』
笹川京子はこの件に関しては何も知らなかった。
綱吉の悩みについては相談を受けたことがあった。
『ちょっと前に、女の子は好きな人を支えるときにどんなものでも犠牲にしていいと思うのかと聞いてきた。ロマンチックだったから、ウンっていったらツナくんは遠くを見た。じゃあやっぱりオレは男らしくなりたい、なんて言って。あたしのこと守るって言ってくれた』
「…………」
六道骸は、屋上の端に立つ。
背後から吹きすさぶ風を受け止めていた。一同からの放心の眼差しを身に受ける。腕に抱えた少年は、背中から突出たものがある。その一点が一同の視線を釘付けにする。
ぽろ、と、骸が手中のものをこぼした。
汚れた床材をごろごろと転がるのは赤い球体だった。
「あげます……。僕の右目……。もう、いらない……から。僕の一番大事だったものですから……、それあげますから……君たちの一番大事なものを……もらいます」
骸は途切れがちに呟く。骸が抱えた少年の左腕から鮮血が滴ってポタポタと音をたてる。まだ誰も動けないでいた。
「追いかけないでください。僕はもう六道輪廻の六道骸じゃない。ぼくら……ただの無力な人間なんです……。これは綱吉くん……なん、です。死んだからもうボンゴレ、じゃ、なくっ、て」
ぐら、と、体が後ろに傾ぐ。
「十代目!」
「ツナ!」
「ツナァ!」
「ツナくん!」
駆け寄ったが、屋上真下のグラウンドに二人の姿はなかった。死体はなかった。
彼らを見たものはそれから誰もいない。
綱吉の生死も、本当のところは調べられなかった。
隼人は殺されたと思ったし、武は返り討ちにされたと思ったし、リボーンは心中したと思ったし、京子は二人でどこかに逃げたんだよねと蒼空に問いかけるだけで自分の考えは保留にした。
その場合は、二人とも大怪我だったから心配だ。
おわり
目覚め

「……ん……、あ……?」
「……………」
「…………!!」
左耳のあたりが、そよ風に遊ばれていると思ったから綱吉は眼を開けた。
途端、予想外の光景が広がっていて、全身が硬直した。自分の部屋のベッドじゃない。懐かしい母の声を聞いた気がしたのも錯覚だった。
ふかふかしたベッドに、覚えはあった。
ここは六道骸の寝室だ。真向かいで、当の骸がぼんやりした目つきで綱吉を眺めていた。
(む、むくろ?! なっ……、寝惚けてる?)
触れるか触れないか、ぎりぎりのところにかざされた手が動きを止めている。
パチリと、眼を開けたのに驚いて静止したようにも見える。綱吉は、眼球だけを動かして、頭の上にある骸の手を確認した。混乱した。夢の中、誰かが、優しく首筋を撫で下ろしてくれて、ほつれた髪を解いてくれた。あの手は、今、真上で躊躇っているものと同じか?
「……………………」
混乱をよそに、骸は、ボーッとしていた。
ひどく緩慢な瞬きをする。
「……起きた?」
こもった声は、喉の中で発音したみたいに声量が低くて聞き取るのがやっとだった。
綱吉は、骸がそんなにも幼い声をだしたとは思えず、唖然とした。
「?!」
「起こした?」
ヒソヒソした声は、妙なところで発音しているのか本当に骸らしくなかった。綱吉はますます動揺する。
問いかけに、綱吉は何も言えなかった。
顔の上にある掌が恐ろしい。今、ベッドであどけない顔をしている六道骸が、今朝方までどんな仕打ちを続けたのかを綱吉の肉体がはっきりと証明する。綱吉の体は痣だらけだ。夜、骸はこう言った。
「今日は一晩かけてあげましょうか。僕はまあそんなに性欲が盛んじゃないですけど。君が、そんなにお仕置きして欲しいって態度ならしないわけにはいきませんからね。他ならぬ沢田綱吉サマの我が儘ですから」
「…………!! …………!」
「その可愛い顔、潰してあげてもいいんですよ? 耳の片方でも千切ってあげてもいいんですよ? ぼく、が、欲しいのは君なんですよ? 君を作るパーツが、どうなろうが、君が生きてさえいれば、あとは、どうでもいいんです」
「……………………!!!」
さんざん泣き喚いた記憶はあったが、綱吉は自分の言葉となると何一つ覚えていなかった。骸が、組み敷いた上から、支配者として拳の鉄槌をくだす度に意識が霞んだ。気絶しても許される筈がなく、骸は腰を使って綱吉を叩き起こした。
「女と……、あの女と寝たんですか? キスしたでしょう。見てたんですよ」
「…………っ」
「勝手に? 拒まなかったのは誰ですか」
「……!」
詰問と共に頬を打たれて綱吉は奥歯を噛みしめた。
唇を切って、血がでてきた。骸は返す手の平でも綱吉を打った。
「!」
「顔ですか? 男のくせに妙にかわいいこの顔ですか? 僕も好きですけど。でもみんなが好きだというなら、ぐちゃぐちゃにしてあげてもいい」
「…………、…………」
「はあ?! 何いってんですか、殴られても感じてるくせに。何ですかこれは? なんで僕の手が濡れるんですか?」
「…………」
「君の体はね、僕が好きなんですよ。僕は知ってましたよ。いい加減、君も認めてしまえば少しは楽に……」
「……」
次第に綱吉はぐすぐすと泣きじゃくるだけになった。骸は、だんだんと責めるのはやめて、綱吉との行為に没頭していった。
そして、意識がようやくクリアになったと思えばこれだ。
思いだすにつれて、涙腺がじわじわと痛むので、綱吉は必死になって喉に力をこめた。もう泣き顔を見られたくなかった。
沢田綱吉の反抗心に、骸は何の反応も返さなかった。
半開きの唇も動かない。
「…………」
無言のまま、する、と、耳にかかった髪をより分けられて綱吉は眉を寄せた。指でシーツを握りしめる。
(なにっ……、考えて。何がしたいんだよ骸は)
やがて、オッドアイがうつらうつらと閉ざされた。寝入る瞬間、普段はとても十五歳に見えない彼が七歳くらいの子どもに見えた。力を失った手が、首に乗っているが、その重みがいやに意識にのしかかる。
「骸」
ずいぶんと悩んだ末に、綱吉が呻いた。
「なんでそんな顔して眠るの? オレはお前のこと許したくない。キライっていっていいと思う。気付いてるだろ。なのになんでそんな顔で……。あれだけ怒って、オレのこと壊しておきながら、骸は」
その先が声にできなかった。喉の奥がツンと疼く。
(骸は、こんな毎日で幸せなのかよ)
六道骸は安らいだ顔で眠っていた。彼と関係ができてから、寝顔を見るのは初めてだ。初めてだった。綱吉は、初めてこころを動かされた気がした。
綱吉は眼を閉じる。
(おれが認めれば楽になるって、ことを、いってた)
(好きって……、言えば……)
カーテンを開けて、朝日でも浴びれば馬鹿げた考えも消えるかもしれない。けど体がうごかない。頭もうごかない。骸の重みを感じたままで、綱吉は二度目の眠りについた。
おわり
鶏小屋

「♪〜〜、♪」
機嫌の良いメロディが体に伝わってくる。首筋にかかる吐息に、綱吉は彼がしようとしていることを察知して片目を閉じた。
柔らかい舌先が尖らせてあって、その舌先が綱吉の左目尻をペロンとした。
片手で綱吉の頭を少し傾けて、前髪を掻き分けると、ペロペロと入念に皮膚を舐めて清めていく。
「…………」
背後の鳥に体重を預けつつ、綱吉は思案する。
こそばゆい羞恥心と、もうどうにでもなれという諦めがごっちゃになって、胸中にくすぐったい熱をもたらした。
(んー。スキンシップ、好きなんだから。仕方ないなぁ……もう……)
「♪」
水色の羽根を持った鳥が嬉嬉として綱吉を抱く手に力をこめた。
舌を長く伸ばして、閉ざされた両目を愛しげに見つめてはペロペロと舐めてきれいにする。毛づくろいだった。
「……………………」
綱吉は、スゥ、と、寝入り始めた。
しかし至福の時間(少なくとも水色のインコにとっては)が長くは続かない。
「きゃー、みてみて! かわいい!」
「くっついてる。ねえねえ、触っていいみたいよ。手に乗ってくれるかな?」
少女の黄色い声とほぼ同時、人間の手が目の前に降りてくる。穏やかな気配を一変させて、インコがクワッとくちばしを開けた。
「きゃあ?!」
「か、噛んだぁっ!!」
「……ん? 骸?」
騒ぎに気づいて、綱吉が目を開ける。
「何でもありません」
「今、悲鳴……」
「何でもないです。おやすみなさい」
再びマブタを下ろせとばかりに、骸はせっせと毛づくろいに励む。綱吉よりも大きい平手でススッと腹の上を撫でたり、腰のくびれをスリスリとさすったり、頬を舌で拭いたりとした。
「…………。そうか?」
綱吉は、ウトウトとしてきて、骸の毛づくろいに身を任せる。
体の表面は短い羽毛で覆われている。羽根が、生えた方向に沿って梳かれていくのは心地がよかった。体がきれいになっていく満足感と相成って極上のひとときだ。これだからエステはやめられない、とかの次元だった。
綱吉が、静かに寝入っていくのを見て、骸はオッドアイをまばたかせる。歓喜に目の奥が光った。
と、
「この子達ですか? もちろん、大丈夫ですよ〜。ハーイ、こっちにおいでー」
店員の和やかな声が聞こえた。
「あ?!」
「…………ん?」
二羽は、ばらばらに分かれて女性店員の手に持ち上げられていた。さすがに店員、手つきが鮮やかで――骸が噛みついても動揺することなく――、二羽を引き離した。
「綱吉くん! 綱吉くんっ!」
慌てて骸が羽根をばたつかせるが、飛べなかった。飼育用のインコは羽根を少し切られている。
「ん……、あ。んん」
「か、かわいいっ。この子、すっごく眠そう」
「お、おねーさん、このインコすごい昇って……、昇ってるよ!」
「その子は一番元気なんですよ。色つやもいいしハンサム、お値段も手頃、おすすめですよ」
「うわ、肩に!」
「綱吉くん!」
手渡されてすぐ、女性の肩までよじ登り、水色のインコは隣に並んだ女子高生の肩を目指そうとする。
「かわい〜」
当の女子高生は、真横でインコが羽根をバタバタさせているのは無視して手中のインコに魅入っていた。
指先では、淡いグリーンの羽毛をくり返し撫でている。人間の指先にやわらかくつつかれて、綱吉はまんざらでもなかった。
「…………」
(気持ちいい……。テクニシャンだな、みんな……)
「綱吉くん! ちょ、浮気! 浮気ですよそれはっ!!」
水色のインコがピィピィと鳴き始めていた。
「や、やだー、もう、暴れすぎっ!」
女性が辛抱しきれなかった。水色のインコが小屋に帰される。
ピーピーと、鳴きながら小屋をうろつくインコを見下ろして店員が渋い顔をする。
「一番、ハンサムなんですけどねー……。ちょっと行動が……。ま、まあ、オススメなんですよ。ほんとに。では、どうぞご自由にお触りになってお好きな子を選んでくださいね」
店員が去った後で、女性客がぼやいた。
「ないわ! コイツはないわ!」
「綱吉くーん……」
ピィ、と、寂しげに鳴いて、インコは小屋の隅に収まった。女子高生の方は、飽きてきたので店内を見渡していた。
「他をみよっか。インコじゃなくてもっと派手なのはー? フェレットとか好きだよ、あたし!」
「……あ、ども……」
小屋に優しく帰してもらって、綱吉はうつらとした口調で礼を呟く。
「綱吉くんっ」
ぴと、と、骸が傍に寄った。
「大丈夫でした? 怪我してません? つつかれて痛くなかったですか? ああ、羽根が少し乱れてますよ? かわいそうに! 今、直してあげますからねえっ」
「んー……、気持ちよかったよ……」
「うそでしょ? 僕のがイチバン気持ちよい筈でしょ」
元のように、骸の胸に収まりつつも綱吉は自分の戻された鳥小屋を眺める。四角い箱に似たカゴだ。見本用、として、インコを展示している。
「にしてもアレだなぁ……。ぜんっぜん売れないな、オレたち……」
「いいじゃないですか、僕らがいっしょにいられれば」
「骸はなぁ……、売れそうなのにな。ンッ、いた、目に入る」
「クフフッ。寝てください、綱吉くん……」
ペロペロと目の上を舐めるものだから、綱吉は、マブタを持ち上げることもろくにできない。綱吉は肩で嘆息した。
(まあいいか……。なんか、毛づくろいばっかされてると、どーにでもなれって気分になる……なぁ……)
安らかに眠り込む綱吉の姿に、骸は至福の微笑みを浮かべる。ギュッと体を抱き寄せ、唄った。
「僕ら、ずうっと一緒ですよ」
おわり
うわき

目が合った。
赤い眼球に六の刻印がある。
彼だと確信した瞬間、サッと身を翻すと綱吉は転がるようにして駆けだした。
人にぶつかったが目もくれずに走る。
彼の目から逃れるには商店街のアーチをくぐって曲がり角を抜ければ充分だが、綱吉は実際にはそこを過ぎた後でも止まらなかった。ぜいぜいと荒れた呼吸で、公園の前まで来た。
(ま、まさか本当にいるなんて――)
ライトブルーに塗られた鉄柵を握って、体重を預けた格好で呼吸を落ち着かせようとする。
目を見開かせた。目撃した映像を脳裏で再生してみると頭痛で視界が眩んだ。
(女の人……。仲良さそうに――。か、かっぷるみたいに。骸の顔に触って)
キスしようとしたところに見えた。
建物の窓枠から上半身を伸ばして六道骸を室内へと誘っていたようにも思える。よくは確認できなかったが何かの飲食店だった。骸は柔らかく微笑みかえしてまんざらでもなさそうに肌の愛撫を受けていた。
ぶるりと体が震えた。記憶が、再生と同時に混濁としていって、綱吉の頭には女のツメに塗られていた赤いマニキュアばかりが鮮やかに蘇るようになる。
「あ、あいつ、なに考えて……。これで何度目だよ」
ボンゴレのこと、好きなんです。つきあってくれませんか?
六道骸がそんなことを言ったのは三ヶ月も前の話だ。なんだかんだで、彼が望んだ通りになったのは二ヶ月前の話だ。綱吉が、骸が実にいい加減でざっくばらんな人付き合いをしていると勘付いたのもその時期だった。綱吉が知っているだけでも、骸には、五人分の前科がある。
(また知らない人だった。か。勘弁しろよ)
じんわり、目が潤んでくる感触に、綱吉は口角を噛みしめる。
鉄柵を握る手にさらなる力をこめた。ギュウ。手の方が痛くなるほどに握りしめる。
(なんなんだ。こんな仕打ち――、かわいい女の子に相手してほしーんならオレって何なんだよ。好きだってのは何なんだよもうっ。骸っ!)
手の甲で目尻を拭って、綱吉はまた闇雲に走っていった。
*****
「どうかしたの、骸ちゃん」
「…………」
角を折れて、背中が見えなくなった。
少しだけ色を変えたオッドアイに彼女は訝しげな声をかける。三度目の呼びかけで骸はまばたきをした。
「いえね、知ってる子がそこに立ってまして」
「あら。女? 男?」
「男です」
彼女はくすくすと笑って少年の首筋をツメでなぞる。赤い流線が夜街をいろどる。
「友達なのね? その子から浮気がバレるのが怖くなったの。骸ちゃん。笑顔が消えているわ」
「その点は、別にどうでもいいんですけどね……」
小声で呻いて脳裏で付け足す。
(その子からも何も、当人ですし)
「じゃあいいじゃない。ねえ、寄ってってくれるわね? 骸ちゃん。今日は私、寂しいのよ。アナタさえよければお店じゃなくてアパートで飲む?」
「それはそれは……。魅力的なお誘いですね」
くすりとどこか皮肉げに骸の喉が鳴る。
六道骸はオッドアイを窄めて女へと眼差しを返した。今夜はこの女性の恋人役をするともう決めてはいるが。
(……綱吉くんも……大概、煮えきれない。逃げだすなんて。僕をひっぱたくか殴るかなじるかすればいいのに。意気地がないんだ。ボンゴレのくせに)
「? どうしたの。気になるの?」
問いかけに、骸は首を左右にふってみせた。
おわり
脅迫
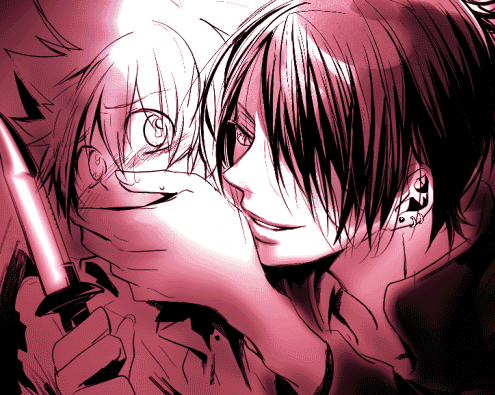
「赤い口紅はどうでしょう。きっと似合いますよ。君に」
「……む……う……!!」
何をされているのか、すぐにはわからなかった。
真横で紅茶を飲んでいたのは六道骸で、獄寺くんや山本にリボーンというお馴染みのメンツに彼を加えてヴィンディチェの下した保護観察処分について談義をした。今だって三人ともすぐ裏手にいる。ファミレスのガラスに夕焼けが映る。一番奥の席というのもあるけど、何度か来たことのあるお店でこんなことになるのが信じられなかった。
「…………?!」
右手側に白く光るものがあった。
サバイバルナイフの刀身だと気付くのに時間はかかったけれど、それが問題じゃあない。正体不明のものがギラギラと間近で光っていて、骸が、オレの下顎と唇をまとめて鷲掴みにして口を塞いできている。
あの骸がだ。
彼が、顔を近づけて、薄笑いをしているのもパニックを煽る。
骸はオレに何をしてて、何を、されているんだ?
頭がついていけなくて、よくわからないから酷く恐ろしく思えて全身に震えが走った。
「聞きなさい。口紅はいやですか? 男の子だから? 日本の古都に習って白いおしろいがいいですか。君の血であやつる化粧は楽しそうですからね、僕が死に化粧を作ってあげましょうか?」
体を動かせない。口を抑えてくる手つきも硬いから、首を振ることもできない。
ぶるぶる、と、出来る範囲で動くと痙攣みたいな異様な震え方になった。
骸が面白そうにオッドアイをごろりと動かす。
「化粧がいやなんですか? 死ぬのがいやなんですか?」
さらに手に力を加えてきた。絡みつくような籠った声は単に人目を意識してのものだろうが、潜んで牙を研ぐケダモノを思わせて、オレの心臓はバクバクと脈打ってる。チワワに追いかけられた時の比ではなかった。
「どちらですか……?」
「…………」
もちろん死ぬ方のがイヤだ。でも手が邪魔で喋れない。
「……んっ……ンン……!」
どうにか喉を鳴らして訴えようとするけど、それすらも骸の思惑らしかった。グニ。サバイバルナイフの刃先が右目のふちに添えられる。骸が舌なめずりするように言う。
「どちらもお好きのようだ……」
「〜〜〜〜っ?!」
横暴に決めつけられて思わず目に涙がにじんだ。
「僕の言うことがわかりますね?」
畳みかけるように尋ねられて夢中で骸を見つめる。せめて目だけででも、意志を伝えないと本気で刺されかねないと思えた。
骸は、軽く笑んではいるが鋭い声で言った。
「金輪際。夢で僕に接触したことは誰にも喋らない。僕が夢を自在に出回れることも、君が僕の夢に侵入できることも誰にも喋らない。アルコバレーノにも、今後、一切、どの場面でもです。質問は?!」
この状況下でまだ発言を求めてくるやり口にゾッとした。
必死に見つめてるのに骸は侮蔑めいた眼差しを返してくる。目をしばたかせると両目に貯まった涙はあふれてしまって骸の指を濡らした。
「……この件に関する会話は僕らが二人きりになった場合は許しましょう。質問が在ればその時にしなさい」
ぶる、と、本気で体が震えた。
こんなヤツと二人きりになるなんて絶対にイヤだ。
店内の喧噪が耳から遠のいていたけれど、足音が聞こえて、それが獄寺くんたちのものだったから冷たいものが胸に満ちる。骸はどうするんだろう。まだナイフを下げない。今はオレの頬に平たいところをベッタリと当てて骸は含み笑っていた。
「いいですか。覚えましたね」
「う……、っん」
言うと同時に手を緩められたので、急いで呻き声を漏らす。
オレの返事に気を好くして骸がまた歯を見せた。
「忘れたら殺しますよ」
骸が体を離した。カチッとサバイバルナイフを収めると懐に戻す。ジャケットを翻す動作と一緒くたに行って、すばやかった。
ほとんど同時に、獄寺くんが顔をだした。
オレは咄嗟に首をさげて泣いた顔を隠す。リボーンが訊いてきた。
「どうした? ツナ」
「何でもない」
体を丸めて、胸を抑えるフリをしながら顔を隠して、手の甲で涙を拭った。まだ体が震えていた。
チラと見れば、骸は、足組みをして紅茶のカップを手に取っている。平然とした態度で訴えた。
「アルコバレーノ。早くしてくれませんか。ヒマじゃないんですよ」
「…………。やっぱコイツ、牢屋に戻しましょうよ! リボーンさん!」
「話がまとまったら帰っていいぞ。お前の能力についてはそれで全部なんだな?」
「クフフフ。どうでしょうね」
こちらを見ずに、リボーンに向かって挑発的な微笑みを作ってみせる骸である。
野球部仲間からの着信にでていた山本が席に帰ってきたのはこの頃で、いつものみんなが傍にいるのに、オレはまだ現実感を取り戻せずにいる。心臓がゆっくり、一呼吸を強く体に刻んでいく。手足が痛いほどに熱い。心底から骸が恐ろしくなってきた。彼は仕切りのない業務用チェアに手をついて身を乗りだしてきた。
「どうしたんですか。ボンゴレ。黙りこんでしまって」
黙るな、という意味だろう。
震えながら顔をあげると、みんなが不審げにオレと骸を見比べていた。同じ言葉をくり返す。何でもないと言ってもしばらくは信じてもらえなかった。当たり前だ。
おわり
たんじょうび!
数えてみると足りなかった。
「おや……? これはまずいですね」
その言葉に、居並ぶ少年達は、持ちあげた顔面をかしげる。
そろって同じ方角に三十度ほどコテンと頭を横にするのを眺めて、彼は口角をナナメにする。ご満悦の表情だ。
「あとで相手してあげますからね……。いい子ですからお留守番ですよ」
一番近く、つまり彼の太腿に片腕を巻きつけてぼーっとした目つきをしている少年の、包帯を巻いてある頭を撫でた。
彼――ブルーブラックの頭髪、紅蒼のオッドアイ、容姿端麗、細い手足、百八十センチに近い身長――外見的には、一見、非の打ち所がなく見える少年は、名を六道骸といって本日めでたく誕生日を迎えた。
骸は「クフフ」とやってオッドアイをぎらりとさせる。口角はふっくらと微笑み、何かを楽しみにするかのようだ。
「脱走するイケナイ子にはたっぷりお仕置きしていいというのがセオリーなんですよ。綱吉くん。クフフフフフフフフフフフ!」
三人の沢田綱吉は、廃墟と化している室内から去っていく骸に、寂しげな眼差しを長くそそぐ……。
「はあはあはあはあ!」
(並盛町はまだか!)と、胸中で叫びつつも沢田綱吉は車道を必死になって走っていた。必死、といっても、人間の体には限度があり二十四時間走りつづけるといった神業は実現できないようにできている。
「……っう!」
汗だらけになった額を手の甲で拭いた。綱吉は、膝を曲げてガードレールに寄りかかった。
そこで、
「つなー! かえろ! かえる!」
腕に貼りついている生き物なのか物体なのかボーダーラインがあいまいな存在が叫ぶ。右の二の腕にがっしりくっついて、さかんに制服のベストを引っぱるのだった。
「う、うるさいなぁ……。それに、重ぉっ。さりげに五キロくらいあるだろおまえ!」
「つなーっ!!」
つなぐるみは、ショックを受けたらしく両目をウルウルさせた。
「うっ。オレをモデルにしてそういう反応すんなよな」
引き攣って、綱吉は、取りあえずはヨシヨシとつなぐるみの頭を撫でた。
知能は二歳児くらいなのか、つなぐるみは、機嫌を悪くしたのをころっと忘れて「つなー」と甘えた声をあげている。綱吉は深々としたため息を漏らした。
「は〜あ……。ったくもー、失敗だったなぁ……」
逃げる前に、つなぐるみに「にげちゃだめ!」とか叫ばれてくっつかれたのもそうだし、六月九日は誕生日だから遊びにきてくださいとかいう骸の誘いに乗ったのもそうだ。てっきり黒曜の他のメンバーがいると思えば、一人もいないし、オマケに――。
「…………」
そばで車が行き交う。ガードレールの内側に体をおろしていると、排気ガスを浴びた。ちょっと堰をしつつ綱吉は青褪める。
「げほっ。……前々から思ってたけどアイツは頭がイカれてるんだ」
「おや、酷いですね」
「?!」
革手袋のざらりとした感じが、あごの下に擦りつけられた。綱吉は背筋をビンッと反らせてしまって悲鳴をあげた。
つなぐるみが、がっしり! という二の腕への絡みつきを緩めた。
「むっくん!」
「クフフフフフフフフフフ。僕と君の美しい世界になれば、このような排気ガスも車もおサラバしますが?」
「ちょっ?! う、うわっ、うわああああ?!」
「僕とサンバでも踊りますか?」
「頭おかしいぞおまえ!」
ヒーッとして後退ろうとしたが、とりあえず状況把握の前にツッコミはしたが、綱吉は本気で手足が動かないのに度肝を抜かれた。後ろから骸に羽交い締めにされて――ホールド状態に近くなっている。
骸は、右手首は自由に動かせるよう、計算した上でホールドをかけていた。
咳き込んだ喉元に触れる。華奢な体の持ち主であるし、性格的な優しさも災いして、むしろこのマンガのヒロインだとか評判がついている綱吉の数少ない男らしい部分――喉仏を、首の皮をへだてた微妙な位置からコロコロ転がしてくる。
「あにするっ……ぎもちわるい」
もがきつつも、綱吉は、顔を顰めた。主婦がプロレスごっこにはげむ若者に向ける「アラアラこの子達は」という眼差しをして通りすぎるのには抗議したかった。
手袋の指で男らしいところをさすって骸はニヤニヤしていた。
「綱吉くんのアダムの林檎、かわいいですねえ」
「何いってんのか理解できねーよ!」
「喉仏のことですよ」
背中に密着している骸の腕へと、つなぐるみがヨジヨジして昇っていく。
それが終わると、ある程度の区切りがついたと思ったのか骸は綱吉を解放した。咄嗟に、前によろけ――そのまま走りだそうとしたが、右手首は骸に掴まれていた。
「さ、おウチに帰りますよ」
「家じゃねえええ!」
綱吉は両手をわきわきさせる。
ブラックジャケットに迷彩のTシャツ、六道骸お馴染みの格好をした少年は、自分の腕にいるつなぐるみに困ったふうな表情を向ける。
「綱吉くんがいやがるんですけど……」
「だいじょーぶ。おれ、むくろすきーっ」
「そうですか。じゃあいいですね」
「よくなーい!!」
もう骸は歩きだしているので、手を引かれながら、綱吉は青褪める。
「なんなんだよ! なんなんだ、あのツナ軍団は!」
「言ったでしょう? 異次元にいた僕を好きな綱吉くん達ですよ。今年はふんぱつして集めてみました。パラレル世界とでもいったほうがわかりやすいですか?」
「そ、そおじゃなくて……、ま、マジで?」
説明されても綱吉は話に筋を通せない――理解の範疇を超えているのだった。中学生の科学では到達できない異常地帯に骸がいるらしいというのだけが、かろうじて、わかる。
「そ、そんなことができるのかお前」
「今日は綱吉くんたちにいっぱい祝ってもらうんです。もちろん、君もくるでしょう? きますよね。帰りますよ」
「話を一人で進めるなよっ!」
つなぐるみは骸の肩までよじのぼって自分の右腕をふりまわしている。コイツもどっかの世界の自分なのか?! 疑って観察したがそもそも動力源は何だろうという原理的な疑問にすりかわった。ついでに、骸に頭でも改造でもされているのかと不安に思うくらいつなぐるみは骸が好きだった。
「ごーごー、むっくんの誕生会、ごー!」
「ゴーですね」
頬を朱色に染めて骸は照れ臭そうにうなずく。
「おいおいおいおい……」
ツッコミしつつ、綱吉はぬいぐるみと少年の後ろ頭を睨む。思いきり、カカトに力をこめた。
「ストォーップ! いい加減にしろよな、骸!!」
「なんですか?」
綱吉が本気でどなると、骸も、足を止めた。
不機嫌そうに眉をよせて掴んでいる綱吉の手首に力をこめてくる。さりげなく圧迫をかけてくる、性格の悪い手口だ。
負けるものかと綱吉は肩に力をいれた。
「誕生日おめでと。でもしつこいぞお前。プレゼントも渡したじゃんか!」
「プレゼント……、それだけですか? ドブネズミでも縄でくくりつけて送り返しますよ?」
「やめろぉおおおうおおお!」
つい想像して真っ青になる綱吉である。
骸は、フンッとして鼻息を荒くする。綱吉の顔に自分の顔を突きつけた。
「他の綱吉くんが祝ってくれるというのに、君は、祝うつもりがないんですか? 君が? 僕を水牢からだした他でもない君が?!」
「そ、それは……、と、とにかくお前はくっつきすぎなんだよ! もういいだろ!」
「だめですよ。なぜか? それは君が自分の胸に聞くべきですね」
「はぁっ?!」
大声で言い合っていたが、綱吉はひときわに大きい声をあげた。意味がわからんと心底から思うからだ。
骸は、今では、綱吉の手首を放して両腕を組んだ。どうでるんですか? と、人を試すようなことが、骸は大好きだ。
「…………っ。知らないよ」
綱吉は、勝負の場からおりる。
しかし声があがった。
つなぐるみだ。ぴんっとして挙手するさまは幼稚園児が先生に注目して欲しくてやる動作にそっくりだ。
「はい、つっくん」
「ぶ」
至近距離で「つっくん」と言われて綱吉は空気を噴いた。自分宛ではないが、ダメージがあった。スライムなら倒せるくらいのダメージが。
「はーい、はいはーい。むっくん!」
「なんですかつっくん」
「お、おまえら、わざとだろ……」
つなぐるみは、満面の笑みで、くちびるがくっつきそうな距離で骸を見上げる。
「むっくんが大好きな、つなが、あつまるからー、つなもいないとダメなの。つなも大好きだから。むっくんが!」
「ふむ……」
骸は、くるりと、顔をつなぐるみに向けた。
チュッとすばやく、くちびるを合わせる。きゃんっ。つなぐるみが嬉しそうに自分の口元に両手をあてる。
「いい子ですね。その通りですよ」
「…………」
後ろによろけて、綱吉はその場に卒倒したくなった。顔も赤味がさしてくる。
骸は、腕組みしたまま不服げな表情になる。
「君も僕が好きならくればいいんですよ。なんでそう意地を張るんですか」
「お……、おれはなあ……」
困窮して冷や汗をにじませつつも、綱吉は、のどをつかえさせる。
「おれが言いたいのはなぁ……」
「僕が好きってこと、でしょう?」
顔を近づけてくる。綱吉は俯きながら鋭く呟いた。
「ここでキスしたら嫌いになるかんな」
「…………――」
骸は、神妙にオッドアイの両眼を細めてしばらく黙った。やがて、うなずく。そうして綱吉の肩に手を置いた。
「わかったら帰りましょうね。一緒に祝いましょう」
「……だ、か、ら、おれはさあ」
と、骸の目はぎらりと危うげな光を灯す。もともと、骸は、策士な割りには短気だった――そのせいで何度か失敗をしている。
「いーから帰るんですよ! 逃げたのは君だけですよ?! まったく不甲斐ない! そんなんでファンクラブが作れますか?!」
「誰が作るかぁああああ?! ってぎゃあああああ!!」
ひょいっと肩に担がれて、綱吉は両手足をバタバタさせた。
――だからさあ!
脳裏で叫びつつ、綱吉は、青くなっていた。
「お、おれが言いたいのはだな、こんなバカみたいなことやって悦に入ってるお前が気持ち悪いとか怖いとか、そーゆう類のツッコミを一万回くらいしたくてだな、でもそんなことしたら朝がくるから逃げたんだってことをだな」
ぶつぶつ言ってみても、当の骸の耳には入っていないらしかった。黒曜ヘルシーランド、特設のキングサイズベッドの上で彼は至福のひとときを過ごしていた。
「あぁっ。もー、骸さん、膝の上でごろごろ頭が動いたら口まで運べないよぉ」
「むっくんー、おっきいむくむくー」
「こ、こーいうことしてやんのは今日だけだかんなっ。どーしてもって言うからだぞ、骸……、キスなんか……、今日だけだよ」
「……………………」
ベッドに寝転がった骸に沢田綱吉が群がっている。
「イクスバーナーを放つと大多数を巻き込むな……」
一人、ちょっと離れたところにハイパーモードに入ったツナがいて炎のこぶしの行き場をなくしている。ごーごーと炎は燃えつづけている。
綱吉は「ふふん、どうですか」とでもいいたげなオッドアイの眼差しを受けつつも硬直していた。
一応、自分も、ベッドに座ってはいるが。

「……し、ししるいるい……」
「なんですかそれ?」
「……感想」
なんだかオレの心が死屍累々のありさまだよと、そんな感想を抱きつつも綱吉はもう逃げる気力すら持てなかった。
「? くふふ。極楽ですねえ……」
天にも昇る心地といった感じで骸は自堕落に綱吉達に甘えていた。綱吉達も(大多数は)骸に甘えているため、チョコレートを溶かしたような雰囲気になっている。
「あ、そこですよ。そこ。あァいい感じです。クフッ。こっちもいいカタチですねえ」
さりげなく綱吉のお尻を骸の手が撫でていたりするのに気付いて、口角が引き攣った。あぐらを掻いて面を青褪めさせるが――。
ベッド。骸にまとわりついている綱吉達。そしてイチゴチョコケーキ。そして赤いリボンのついたテディベア……。
まさに綱吉天国とでも言えそうな光景を前に、綱吉は、今さらながらに思うのだった。
(骸にテディベアなんかプレゼントできたオレもそうとうイカれてるのか……? いやいやいやいや……。比較的、マシっつーか軽症だよな、うん)
ごろごろごろ……。
六月九日はごろごろして終わった。
おわり
ハローホロウ

淀みなく、キャソックのボタンが外されていく。
「さて――」
色事をしょっちゅうやっていたかのように、彼は蠱惑的な微笑みが板についている。脱ぐのと同じく慣れた手つきで、相手の腰を持ちあげ、膝に載せた。
「うわぁああああ?!」
吸血鬼のほうが、全身をビクンとさせた。
「何を鶏のように驚くのですか。さぁ。どうぞ。吸血鬼殿」
「うえええ?! で、でもっ――」
「僕を殺してみせるのです」
「……っ!!」
ヒトにしては異端な――赤と青の双眼が、吸血鬼の目のなかでギラついた。
瞳の距離は近い。眼差しを喰い込ませながら、下顎をわずかに左へとクイと持ちあげて、噛みつきやすいように喉首を晒した。
口をパクつかせた挙げ句に、吸血鬼は確認をこころみる。
震えた、気弱で、おどおどした、およそ闇の軍勢の一味とは思えない声で――そもそも男にはこの個体に近いのは闇の悪鬼ではなく羊飼いか村娘かに見えたが――、ともかくもか弱い声で仰天した。
「お前、死んじゃうんだぞ?!」
「わかってますよ」
「いやいやわかってないよ! ゾ、ゾンビになるんだぞっ。おれは男だぞ?! オスの吸血鬼で――」
「見てわかってるつもりですが? 顔はともかく、体が貧相ですからね」
言うついでに、真っ平らな尻を撫であげれば少年吸血鬼が甲高い悲鳴をあげた。
「ひゃぁあああああっ?! ヤ、ヤメロ!!」
人間でいうならば犬歯がある位置に、牙が突き出ている。男のオッドアイが牙へと注がれる。憧憬に似ているがまったく違う感情が滲んでいた。
「男が男を喰えば、女が女を喰えば、生ける屍へ変わる……。いわゆるゾンビです。神は同性愛を禁じていますからね。初歩ですよ。もちろん知っています」
「なっ……、な、ならさぁ……。せ、せめて……、カワイイ子を紹介しようか?」
「吸血鬼が獲物をよそに譲る?」
信じられなくて尋ね返したが、すぐに、個体差はどうでもいいと思い直した。
「間に合ってますよ。御託はいい。殺していきなさい」
「や、そんな、こ……殺す気……で来たのは確かだけど……。こんな展開は困るよ……。ゾンビはケモノ以下だぞ? どんなアンデットだか見たことないのか?」
「神父ですよ。たくさん殺したに決まってるでしょ」
「じゃ、じゃなおさら頭おかしいんじゃないかお前―っ?!」
面倒臭く思いながらも、男は順を追って話しましょうと告げた。
膝上から、吸血鬼の腰を支えている指先から、震えが伝わってくるのだ。
どうやら吸血鬼は吸血鬼のくせに怖じ気づいているらしい。
まずこの子を宥めることから手をつけよう――。
そう思えたが、だがこれから殺されようとする人間の思考回路としては極めて異常で可笑しくなった。
男の浮かべた嘲笑に、吸血鬼はますます目玉を唖然とさせた。
*
「護衛軍は何をしているんだ!」
怒号を後ろに、神父は三叉の槍を握ってやや背を反らして立っていた。雨が降っている。キャソックの裾が汚泥の泥を引くほど酷い土砂降りだった。
槍の先には、澄み切った青い血がべっとり付着している。
「そうだそうだ!」
「領主を引きずり出すんだ。こんなんじゃオレたち殺されちまう――」
「お待ちなさい」
ブーツのカカトを迷うことなく泥に突っこませて、神父が歩み寄った。
青く濁る矛を、雨雲に掲げる。
「見よ。神は我らを見捨てていない。我らは神の矛です――、神が与えたもうたこの力が何よりの証拠! 神父には魔を殺す力があるのです! そして教会は貴方方も軍も領主も何もかもを見捨てませんよ。さぁ、民よ、共に戦いましょう!」
ざわ……ざわわ、どよめきは、急ごしらえの演説によってまとめられていく。神父が低い声で高らかに叫んだ。
「ジャンヌに続くのです!」
三叉槍が、遠くの空に見える暗闇に向けられて、神父が誘う。
――命を賭けた戦場にいながら潔いほどの笑顔である。民衆が、声をあげて、泥を蹴りながら闇に向かった。
(骸ク〜ン)
と、そのときに声を聴いた。
「誰ひとり欠けることなく生き残りなさい。戦い抜くのです。それが神の意志です!」
「おおおお!」
人波の先頭を走り、だが、神父は途中で道を曲がった。手近な男にコチラの悪魔は協力なので自分が処理すると告げる。
「神父さま、ご武運を!」
「貴方方もね」
初めから、どこが手薄なルートであるのか把握しているから楽ではあった。アンデッドに占拠されつつある城下町は、あたりに赤や青の血が散っていた。
城壁の前。とあるところで足を止めた。
白髪の男が待っていた。白い法衣でハードカバーの聖書を片手にしている。宣教師の姿で、ずぶ濡れだ。
「やっ。むっくろクン。ご苦労さま」
宣教師は、気楽に、聖書を抱いていない方の手をあげる。
「けっこう活躍したみたいじゃん。時代が時代なら、功労賞でも出たんジャン?」
「白蘭……。首尾は?」
「もち、カンッペキさ。領主サマの血はユニちゃんに飲ませたよ。これで後はこの街をこっそり食料庫にさせていただくだけさ」
「約束の金庫の鍵は? 金を貰うまでは攻撃を緩めませんよ」
「うわぁ、それって脅し?」
口許に手をやって、びっくりまなこをしてみせるが、白蘭はすぐさま左右の口角を持ちあげて微笑んだ。
純金の鍵束を、人指し指に引っかけて差しだす。落とされたものを神父が引ったくった。
「これから、どうするの?」
白蘭の質問には睨みが返る。
「地元に戻ります」
「また戦争があった場合は?」
「呼ぶがいい」
「ハハッ、二重スパイなんて役、よくやるよねぇ。面白い人間だな〜。でもよかったの? ここの領主サン、もう死んだも同然のブタの扱いになるわけだけど、骸クンとしては、」
「僕を拾って育てた男ですね。でも、だからなんですか。どうでもいい」
鍵を懐にいれて、神父は城門へと歩いていく。
「冷たいね」
ザー、降り続けている雨の中に男の言葉が落ちてくる。
「僕の寝室でお仕事してみる? 骸クン」
「断る。君とは趣味が違いますから。さようなら。永久に」
「う〜ん、ツンツンだねェ」
雨に混じって濃い霧がでている。諍いの声がどこかで跳ね返って鼓膜に沈み込んでくる。
神父は、もうふり返らず、鍵束をカチャリとさせて仕事の続きをしに行った。
*
「ま、まさかそこの積んであるのって」
少年吸血鬼は、教会の片隅に何気なく積んである紙片を見やる。
「領主から奪ったものですよ」
「ひぃいいい?! 恐ろしいことを! 吸血鬼殺しとして有名なのに!」
「それはそうと、ご理解いただけましたか? 僕の理由」
「今の話で? 先の戦争でスパイがいたのは知ってるけど……、でも、オレはただお前が民衆を煽ったから殺せって……」
「おや。では君は末端だ。スパイは始末しておくものですよ」
平然と言ってのけて、片手を広げる。
「実に簡単に予期できた展開です。返り討ちにするつもりで受けた仕事でした。でもね、あの戦争で僕はいささか疲れていたようだ」
「疲れた?」
「僕が僕であることに」
オッドアイが静かに眼瞼を被せる。
しげしげと、顔を覗きこまれているのを感じた。吸血鬼はやっと相手を正視できたらしい。
男は、出し抜けに尋ねてみせる。
「僕って、美しいですか?」
「は、はあっ? 何でいきなり。何だよ」
「いえ。興味あるみたいですから」
「…………っ?」ただならないものを感じて、吸血鬼が口角を引き攣らせる。
怯えながら尋ねたのは、しかし違う内容だ。
「魔力を持ってる神父だから……、危なくなったら逃げろって言われてるんだけど。友達に」
「吸血鬼に友達がいるんですか」
「いるよ」
っぷ、男が吹きだした。
「君は、相当、変わった個体みたいですね……。そうですか。気に入りました。さぁ血を飲むといい」
後頭部を掴んで、首筋に顔を埋めるように抱いてくるので慌てた。
「ちょっ、や、やめろよ。こんな展開で血なんか飲めないよ。せめて戦わないかっ?!」
「嫌です。もう戦意が失せました」
男は楽しげに小首を傾げながら言う。吸血鬼は、ポカンとなったが、その顔を見て別の興味が湧いたのか彼はすぐ尋ねた。
「君、僕が教会に帰ってきてからなんて声をかけたか覚えてますか?」
「? オカエリっていったぞ」
吸血鬼としては、最高の殺し文句のつもりだった。
神父が根城に帰ってきて――、自分のような吸血鬼が、待ち構えているのだ。ホラーシチュエーションとして悪くない。
「あ、でも、お前がびっくりしてたから怖がらせすぎるのも悪いかなって思って、オカエリってだな……」
「それは、思ってたよりぜんぜん弱そうな吸血鬼がきてたからですけど」
「んなぁっ?!」
「でもそうです。それで疲れちゃいました」
「はああ? まっ、待てよ。わかったぞ。お前、今、ヒステリーってやつ起こしてるだろ。人間の病気だろ」
「おかえりなんて、生まれて初めて言われました。だから唐突にわかりました。僕が欲しかったのって、そういう生活だったんだなぁってね」
深く溜息をついて、神父は異端の両眼で遠くを見やった。悪魔の青い血の色をした左目と、人間の赤い血の色をした右目がひび割れたガラス向こうの光を寄せる。
ステンドグラスの鮮やかな明かりは、離れたところに落ちている。紙片の近くだった。
「人形として慰み者でもなく神父として神の言葉を騙るのでもなく悪魔として人民を売るのでもなく、単なる一人の個体として、誰かに認めて欲しかった」
オッドアイが、色とりどりの明かりで光っている床を見つめた。ステンドグラスに写る聖女は、床では滲んで輝く。
予想外の答えに、吸血鬼は喉を詰まらせた。
膝上の子どもをあやす調子で、神父が、右耳に息を詰めてくる。
「君は、ちょっと面白い。個体として認めてあげます。だから殺していいですよ」
「ど、どうしてそうなるんだ?」
「人生で選択を間違えることってあるではないですか。この世ではもう僕が欲しい世界は永遠に手に入らない。だから、僕はもう辞めてもいい」
「な、じ、自殺なんて地獄行きだ」
「だからゾンビでも似たようなもんだと言いたいのですよ。さあ。かなり若いと見受けますがね、吸血鬼殿、男になっていただきましょう」
吸血鬼の顎に指をかけ、持ちあげてやりながら、男が顔を覗く。
さすがに気分を害した。
「バカにしてんのかっ。噛むぞ!」
「どーぞ」
詰め襟を指で摘み、下着をチラッとみせる婦女子と同じ手つきで首筋を晒してみせる。
「お、おう、喰ってやるよ。人間の変わり種ッ!」
「くふふふ。よく言われてます」
体重の軽い少年吸血鬼を膝に載せたまま、神父はもぞりと動いて足を組み替えた。尻の下での動きに吸血鬼が眉を潜める。
「い、痛くても知らないからな……」
「くふっ」
「は、鼻で笑うな。人間だろおまえ」
「こんな短い間だけのお知り合いですが、でも君には言葉で勝ちつづける自信がありますね。弱点が多そうな顔をしている」
「なあっ、痛いんだぞ! 吸血鬼の牙は!」
「いいから殺していきなさい。僕に死という名の至上の快楽を与えてください」
「死ぬのが気持ちいいのか」
「ものの例えです」
「……っ、に、人間ってワケわかんねー」
本人を前にぼやいてしまいながら、吸血鬼は瞠目する。が。――満足げな嘆息が神父の鼻腔からあふれていった。
闇に身を明渡す淑女のように、体から力を抜く。
吸血鬼の少年が、腰をやっと持ちあげて自分より背丈のある男の首を齧ろうとしている。
「……好きでもない相手の血を吸うのって、好きでもない相手を抱かされるのと同じなんでしょうね」
「え、な、なんなんだよお前はもー、いきなり」
どこに牙を立てるか、首を触って場所を選んでいる途中だった。少年が顔をあげる。
「そういう経験は昔からたくさんありましたから」
「は……? えぇっ……?!」
男の美貌と、すべらかな肌とを見比べて――、吸血鬼は顔面を真っ赤っ赤に茹で上げた。男が逆に感心するほど激しく、大げさに驚いて悲鳴をあげる。
「わ、わわわ、わああああああ?!」
「童貞ですか。ほお」
「ば、ばかやろーっ! 何いうんだ!」
慌てて、骸の顔を引っ掻こうとしたが、吸血鬼の鋭利な爪で傷をつける前に冷静になれた。恨めしくもなった。
「お前、ワザと怒らせようとするな」
「おや。わかりました?」
「そんなにさっさと殺されたいのか……」
吸血鬼は喉を震わせる。男について思い馳せるような沈黙が、漂った。
「……」神父は、もう言葉もなくただ最期を待った。
やがて、吸血鬼の覚悟が決まる。少年は口角を小さく噛んでから、唇を寄せた。人間の血の色をした赤目玉をくだった先の――、白い首筋に、標的を定める。
「……ん」
ぺろ、ぺろぺろ。
舌で大切に舐めていく。ここから食べるのだ。
吸血鬼のふわふわした髪の毛で頬をくすぐられながら、男はまばたきを繰り返した。
「吸血行為の前に、唾液を塗りつけるんですか? モスキートじゃあるまいし」
「ち、違うよ。汚くてごめん」
吸血鬼は躊躇いがちに目玉を上にやる。八の字になった眉根が目玉の上についていた。
「濡らしておいたほうが、あんまり痛くないかと思って……」
これには、男も驚いた。
「初耳です。そういうものだったのですか」
「いやわかんないけど。噛まれたことないし。違うかな?」
「…………」
一瞬でも注目してしまった自分がバカみたいで、神父が半眼になる。が。ものの数秒で思い直した。
下唇だけで浅く微笑み、こぼれた吐息が吸血鬼の髪にかかった。
「いえ、きっとそうでしょう。たっぷり舐めてください」
「? う、うん」
唾液を塗りつけられながら、彼は、ケロッとして言い放った。
「処女を犯すときもたっぷり濡らすものですからね。幸いにも僕はバックバージンはまぁ領主の趣味の問題で……」
「のああぁあああああああギャァアアアアアアア! ヤメローッ!! 食欲が削がれるだろーが!!」
「醜悪なブタ男を毎晩抱かされた僕の気持ちは果たして君にわかりますかね?」
「聞きたくないっつーの!!」
半脱ぎのキャソックの詰め襟を掴んで、吸血鬼が荒ぶった。
「そ、想像しちゃったらウマいものもマズくなるだろ!!」
「したんですか? ご愁傷様です」
陰険な半笑いを浮かべて、しかし腕では吸血鬼の背中を硬く抱き寄せる。
「もういいでしょう? 逃がしませんよ。そろそろ挿れてください」
「や、やめっ……、変な意味に聞こえる」
「そういう意味ですから」
強気どころか、今にも犯してきそうな目をしている……。吸血鬼が、ゾッとしている間に刺激がきた。
れろ。尖った耳に、舌が当てられる。
「ひゃあっ?!」
甲高い悲鳴があがった。
「焦らすのもいい加減にしないと僕が食べてしまいますよ? まぁ、顔は悪くありませんから……、別に――、さぞや小さくて狭いんでしょうね、君の茨は」
「さささささりげなく下品極まりねえ論評すんな!!!」
耳をしゃぶり、吸われていると変な気分になりそうだ。吸血鬼は慌てて神父を両手で突っぱねた。
「食べる! 今ゴハンにする!」
「クフフ。遅いんですよ」
「っ、へ、減らず口!」
怒ってから、吸血鬼は自分の髪の毛を横にどかした。男の首筋に口を押しつける。唾液で充分に濡れてヌラヌラしている地肌に――、牙を立てた。
「――、……」
ごく、少年が唾を飲んだ。
「…………」神父はオッドアイを閉ざす直前まで引き下ろして待ちの姿勢である。
死はもう受け入れている。死なない死者となって彷徨うのも。思考回路の消滅こそが神父の望みだった。
「……チクってするよ?」
「ええ」
素っ気なく呻き、神父は完全に瞳を閉ざした。
吸血鬼が、男の肩を掴んだ手に力を籠める。
ぐわっ。牙が剥き出しになった。刃はすぐ皮膚をもぐり、血をえぐり出す。口をも使ってちゅうちゅうと鮮血を飲んでいった。
「……う……」
鼻にかかった呻き声が、神父の体からこぼれた。
初めて苦痛を訴えた態度である、が、そのときには吸血鬼が積極的になっていた。吸血の恍惚感で目がうっとりしていて焦点があやしい。夢中になって飲んでいる。
喉が上下を繰り返し、ドクンドクンと神父の心音を二人で分け合った。
「…………っ」
神父は、静かに冷たくなっていく肢体の感覚を受け入れていった。この先に待つのは果てのない永遠の死だ――、屍肉を貪るだけが生き甲斐のゾンビである。
その筈、だった。
*
「これは、なんです?」
横たえられているベンチから、体を起こした。
端っこには吸血鬼が膝を抱えて座っていた。教会で、たくさん並べられた長椅子の最後部だ。彼は短く挨拶する。
「オカエリ。神父さん」
「……僕の名前は六道骸であってますか?」
「知らないよ。そういう名前だったのか」
「僕の名は骸だ。どうして……、なんで名前を覚えてるんだ?」
思考が回ることに愕然として、神父は自らの首筋を触った。
牙の跡が、ふたつ――。指には真新しい血がついた。
愕然とした。もしかしてそうだったのかと尋常ではない衝撃を受けた。
「メスだったんですか?!」
「ちがーう!」
複雑そうに叫んで、少年が立ち上がる。
わざとマントを揺らして腕を伸ばし、腰に手をつけた。精一杯の威圧感の演出である。
「――臭いでわかってはいたんだよ。お前、ハーフだろ。魔性と人間の混合だ。だからまぁ……、なんか可哀相だったし。あんな話を聞いたら殺せないよ、オレには」
「あんな話?」
骸には、特別に不幸な事情を話したつもりがなかった。今の荒れた世の中では比較的マトモな部類だ。
吸血鬼は、躊躇いながら骸の名を呼んだ。
「骸って、死体の名前をなんでまた……。まぁ、いい。お前のハーフの血に働きかけたんだ。一個だけ同性でも吸血が許されるパターンがあるのを知ってるか?」
「なんだ」
「知らないよな、そりゃ。お前が領主さんの愛人だったとかいう話でな……。ピンときた。オレが、男の妻になるつもりで吸血すればいいんだ」
「おとこのつま……」
聞き慣れない響きを、口内で転がす。
「えっと……だから……、たった一人だけならオレたちの神さまは許してくれるんだ。女の快楽を知るために一人とだけならそういうことしてもいいって」
言いながら、耳まで赤くなっていく。
「…………」度肝を抜かれて何も言葉が出なかった。瞬間的に思考が停止したのだった。感情すらも無になる――。無風地帯のようなものだった。
何もかも予期していなかったが、聞き間違いにしか思えなくて確認は取った。
「……僕の妻なんですか? 君が。男の?」
「ばーか!!」
吸血鬼は、恥じらい混じりに舌打ちした。
「オレ、別に、男の恋人作るつもりないからお前で消費しても構わないってだけだ! ただでも吸血鬼化させた責任は取るよ。オレたちの村にこいよ。オカエリっていえる友達くらいできるだろ」
「…………」
二度目の衝撃で、オッドアイが真ん丸になる。
しばし――、考える時間が欲しい。
「そうだよな。わかった」
吸血鬼は、骸の訴えに歯を見せた。こざっぱりした印象の笑い顔である。
「明日またくる。ああ、オレの名前、ツナっていうから。沢田綱吉――」
カツン、靴を鳴らして吸血鬼が出て行こうとする。
「綱吉」
骸が呼び止めた。
目覚めたとき、キャソックを体にかけられていたので、今はそれを背中に引っかけている。
不満げに眉を寄せている元神父に、吸血鬼少年は小首を傾げる。
「死ぬたがるなんてよくないぞ?」
「つまり、君は、僕を認めたというわけですね? ダンナにしてもいいという意味で」
「え? いや、かわいそうで」
人間でいるには難しい思考と性格を持ってるみたいだから、いっそのこと……、綱吉としてはなけなしの気遣いなのだ。
骸が、綱吉がぞっとするほどの笑みを浮かべた。
優しいのにギラついている微笑み。オッドアイが、笑っているのに殺気立っている。
「童貞なんでしたっけ。とりあえず、やっと死ねると思ったのに期待を裏切ってくれた仕返しをさせていただきますよ」
「え。え。えっ?」
手首を握られて、折られそうな腕力には目を剥く。
「それと、男の妻とやらの味、どんなものかみせていただきます」
「いやっ、ちょっ、オレの言ったことわかってるか? 妻にはなる気がないっつー」
「僕がこんだけ性欲を掻き立てられるんですからチャームでもかけたんでしょう? カマトトぶらないほうがいいですよ」
「お、オレなんもしてないぞっ?!」
心外だと叫ぶが、神父はキャソックを床に広げている。その上に綱吉が転がされた。
「ぎゃ、ぎゃあああっ?!」
「みえます? 牙が」
口に指を突っこみ、生えたての牙を露出させる。跪きながら綱吉の頬を齧り、唇を齧り、牙で浅く簡単に引っ掻いていった。
ディープキスを試みてみると、慣れない位置に牙があるので何度かぶつかった。がちんッ。
「っつ! や、待てよ……っ。いた、牙痛いよ、っていうか、困るよこんなの。オレは吸血鬼だぞ! お前を吸血鬼化させたんだからお前の親だろーが!!」
「でも妻でもあるんでしょう?」
口を大きく開けて、すると骸の口角からも呑みこまない唾液が垂れていった。牙の当たらないキスのやり方を模索する。
「うううっ。ひゃめっ……ンッ」
舌を吸われて、綱吉が肩を竦める。
「――」それを見ている内に骸もいささか戸惑った。牙を刺せるくらいに、力をいれて唇の肉を挟む。
「んん!」
「よっぽど強力なチャームを使ったようですね……」
「っ、っ?! っぷあ、ぷはっ! はあっ、ちょっと待てよ、オレほんとこういうのは経験ない――」
「ほう。それはすばらしい」
吸血鬼のマントを落とし、脱がせながら、新米吸血鬼がほくそ笑む。
「今まで境遇に感謝したことはありませんでしたが、でもこれは面白い。僕の持てるテクニックのすべて――、君にじっくり叩き込んであげますよ」
「へ……、ど、どういう……意味で」
「クフフフフ。お楽しみに」
次のキスは、真っ赤になっている綱吉の目の下に宛てた。
その後、行方不明かと思われるくらいに時間をかけて村に帰った吸血鬼は、連れている男をしぶしぶと夫だと認めたと言う。
おわり
お兄さんと温泉!
(※そして恐らくこの話(かイラストが!)原因で運営さまより掲示板を削除されて
割れ鍋は終わりました(・▽・)ありがとうございました!)
「きばりまっさかいよろしゅうたのんますぅ〜!」
女中が去って、絢爛な客室には青年と少年とが残された。
夕食の配膳が済んだのだ。
共に着ているコットン素材の浴衣は、深緑色で手触りがいい。
シンプルな姿だからか、綱吉と違って彼の華やかさが目を惹く。綱吉には何だかショックだ。
「綱吉くん。これも、おいしいですよ。素材の味をよく活かしている」
(素材がぜんぜん違うんだな……)
役者が違えばどんな服でも映えてしまう、まるでそのお手本だ。
六道骸は今年で二十五歳になる。恋人になれてからまだ日が浅くて、旅行も今回がはじめてだが。綱吉は歳の差やら感性の相違やらを感じて仕方がなかった。
視界に影が差して、はたとする。
驚いているあいだに口のなかに箸の先っぽを押し込まれていた。
「んッ、む。あ、ありがとうございます」
「マグロ、おいしいですか」吐息が微かにかかる気がして身がこわばる。夢中でうなずいた。
醤油はついているがワサビの味はなかった。
(わ、ワサビは、鼻につんとくるからヤダって言ったけど……)
以前、何気なく言ったのを覚えていたのだろうか?
綱吉はまだ中学生だ。でも、子ども扱いは複雑だ。
「僕も今食べたんですよ。蕩けるでしょう。大トロは? 綱吉くん。軟らかくてどろどろしていて、噛み潰していると弾力が返ってくるでしょう……、活きがイイ証拠ですよ。若くて肌がぷにぷにしてるんですよ」
「……おれ、友達から、ツナって呼ばれて……」
食べ物の「ツナ」のほうは原料が主にマグロだ。
「ええ。知ってますよ。おいしいですよね。はい、綱吉くん。大トロですよ……、あーん?」
「……っていうか、ですね、なんで、骸さんの膝に乗ってるんですかオレッ?!」
汗でだくだくになって綱吉が一生懸命に俯こうとする。
骸青年はくすくすと笑っていて、逃げた唇の先に赤身のトロを運んだ。青年が小首を傾げると、結んでいない長髪がはらりと浴衣をすべる。
「アーン。くちゅって噛むんですよ。綱吉くんとおんなじでトロトロですからね、この大トロは」
「か、からかわないでくださいっ……!」
(さっきからご飯食べてるのか変なイジメ方されてんのかワケがわかんないし、お、おれの勘違いじゃなかったらァッ!)ひー、喉で悲鳴をこらえてどうにか面をそらすが。骸の膝に横座り、背中は彼の大きな手のひらで支えられている姿勢だ。逃げられない。
「あ、あむぅ…ッ」
唇の真前でうろつく箸が、強引に唇を割ってくるので綱吉は舌をからめて大トロを口に入れた。
すぐ溶けてきて舌に浸みてくる、と、目を剥いた。オドロキだ。
「お、おいしい。このマグロ!」
綱吉を見つめながら骸青年は上機嫌にうなずく。眼鏡は外していて、裸眼のオッドアイが爛々と光っていた。
「ですねえ。このトロトロで柔軟な食べ応え、僕好みですよ。いろいろなものを思いだします」
「…………っ」腰回りをナデナデ撫でさすられながら、なので、妙なふうに捉えてしまいそうだった。綱吉は先走った恥ずかしさで顔を反らす。
綱吉に食べさせたのと同じ箸で、骸はイカのお刺身を口にしていた。ぱく。
「これもいいお味ですね。くにゃくにゃして捉えどころがなくて、噛んでいる内に熱く熟れてきて……、官能に火を点ける。さあ、君も」
(ピー音をどこかに入れなくていいのかな……)
骸の膝上でボーとしながら、はやくもお腹いっぱいの気分だった。骸との旅行デートは濃密すぎて、綱吉はずっと頭がパンクしそうになっていた。骸がクスッと鈴声を鳴らした。
「……君は、もう小手先の悪戯を加えなくてもずっとトロトロになりかけてますけどね」
「骸さん?」背中を撫でながら、いやに低い声だった。でも聞こえなかった。見上げるとニッコリ笑顔がある。
「クフフ。僕の十年をこうも君が報いてくれるなんて、幸せです」
「!」目を瞠る。ニコニコしながら片思いを回想されて――しかもこんな至近距離でだ。頭どころか心臓がパンクする。
「むッ! 骸、さん、やっぱオレはあっちの席で食べる。こ、ここじゃ落ちつけないっ――」
「僕と触れあっているのに?」
「んっ?!」首筋に、息がかかった。
骸の朗らかな笑みはいともあっさり消えていて濃艶な呼吸がそこにある。浴衣の解れ目からは鎖骨の盛り上がりが見えた。
「それとも、お兄さんと触れあっている、から?」
「……ご、ご飯食べれないようっ」
腰回りをすっぽり包めそうな程の手のひらが、なでなで、腰のあたりの骨をさすってくる。
「部屋食がいいって言ったのは君ですよ。たっぷり甘えてくれて構いません」
「こ、こんなふうに、座るなんて思わなかったから! 骸さんだって重いと思うんですよっ、さっきから乗ってて――」
「羽根みたいですよ?」
「うわぁあああ?!」
反射的に悲鳴をあげたが、足をバタバタさせても骸は動じない。わかりました、そう呟くと綱吉にも箸を握らせた。
膝上であっても自由を与えられたらいくばか安心だ。息をつく。が。
「僕はそろそろお野菜が欲しいですね」
にっこりして、骸が綱吉の目の上に顔を近づけた。
「……えっ。あ」里芋の煮物を箸でつかんだところで、停止する。すかさずに骸が止まっている手首を掴んだ。
「何をためらうんですか。食べさせてくれないんですか?」
「……えっ? ええっ――?」
唇が近づいて、綱吉の箸を持つ手が震えはじめた。
腹の底から胸のなかいっぱいまで、甘酸っぱい辛酸が拡散される。綱吉は途方に暮れた。眉が八の字に寄りあがる。
「そ、そんな、おれ、できないで……す」
「どうして?」
三日月が拡がるような笑みが彼の口角を持ち上げていた。
綱吉はますます混乱する。
「だ、だっ……て」
骸が、どこかおかしい――決定的に――憧れのお兄さんとは言い切れないと今はもう知っている。常識で計り知れない部分がデカすぎていっそ不気味だ。そういう領域に片脚を引き摺られてる気がして、しかしどうしてか甘ったるく感じて、当惑する。
かぁああ、骸を見上げながらも頬が燃えていった。
「へッ、変だから、です。恥ずかしい」
やっとの思いで拒否を試みる。
しかし骸は引かなかった。笑顔のままだ。
「そもそも温泉デートなんて恥ずかしいものの塊を所望したのは君ですよ? 好きなだけ甘えていいんですよ? 誰も見ていませんから」
「……っ」こちらに来てから、何回か体を重ねたが野外だったので甘えるどころじゃなかった、それも事実だ。
(でもこれだとオレが骸さんを甘えさせてるんじゃ……?)疑問は尽きないが、手にぎゅうと力を込めた。骸もあーんってしてくれてはいるのだ。
綱吉の目を眺めていて、彼も変化を読み取った。口唇をナナメにひらかせる。
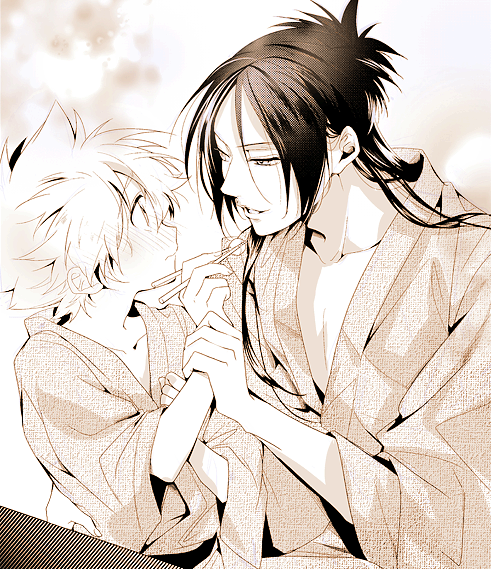
「む、むくろ、さん……」
覚悟を決めて差し出した。
薄く開いている暗闇に落とそうとする。
「あ、あーーん」
「ん」ぱく。箸の先が飲まれて消える。
箸を引かせるタイミングはどうしようと困っている内に向こうから頭を引かせた。れろ、汁に濡れている箸にかすかに舌を這わせていったので、赤い粘膜が覗いた一瞬は総毛立つような心地がした。
(や、やらし……っ)
「クフ。すごい、キスして欲しそうな顔してますね……。僕の綱吉くんは」
「え、あっ? え?」ビックリしすぎて変な発声になる。顔がボンッと赤面した。
赤に青の原色オッドアイは熱っぽく見つめてくるのに、相反して言葉は冷静だ。骸が求める。
「次は、そちらのインゲンが食べたいです」
「え。つ、次もぉっ?」
「僕もやってあげますから。ね? 茶碗蒸しはフーフーしたげましょう。ヤケドを負ったら大変だ」
「う、うぅう」
器の蓋を取り、陶器のスプーンを片手に躙り寄る青年に怖じ気づく。
知らずに膝をモジモジさせていた。
顔中がもうまっかっかで、息も苦しい。
「こんなんじゃ、ごはん、一時間もかかっちゃいますよ?!」
「いいじゃないですか。このために全てのものを先に出してもらったんですから」
「んなぁっ?! さ、最初から?」
インゲンを箸で取りつつ、目を丸くする。
骸が顔を近づけたので慌てて箸を唇の先に持っていった。
腰をしっかり抱いた手は腋のすぐ下に昇ってきていて、手首から先だけを出す。それで骸は茶碗蒸しを取り、スプーンを反対の手に握った。あむ。綱吉の手から、インゲンを食べつつ。
「……はい、綱吉くん。今度はこっちですよ。まだ熱いですからね」
ふー、スプーンを吹けば湯気が踊った。粗熱がじゅんと綱吉の頬を湿らせる。絶句していた。
(ひ、ひぃいいいっ! 一時間もこんなふな食事したらオレ死んじゃうだろぉ!!)
「あーん」
「んむッぅ」
スキ有りとされて、ひょい、口にスプーンを突っ込まれる。茶碗蒸しは甘かった。青年は満面の笑みである。
「おいしいでしょ。綱吉くん」
「ん! んう、ん」
頬の奥にちょっとだけ当ててくるので、ホッペタが少しだけボコりとする。ハムスターが餌をいれるか、あるいは、――銜えさせられた感覚がサッと蘇ってきて綱吉が両眼を惚けさせる。
「……ほら、そうやって」骸がナナメ笑みを釣り上げた。
「君みたいに溶けてくでしょう? お口にいれると。おいしいですか」
「う、……うん……」
とんでもなくやらしいことをされてる気分がして、綱吉の指先がひくんと蠢いた。
スプーンを口から抜かれると、あやうく唾液が口角から垂れそうになった。口を拭う綱吉に青年はニッコリを深めながら薄眼を開ける。耽溺から口角が歪んだ。
「今すぐ食べちゃいたいですよ、まったく」
夜は長く、まだ料理もたくさんある。
おわり
ほかにもハロウィンやら誕生日やら、
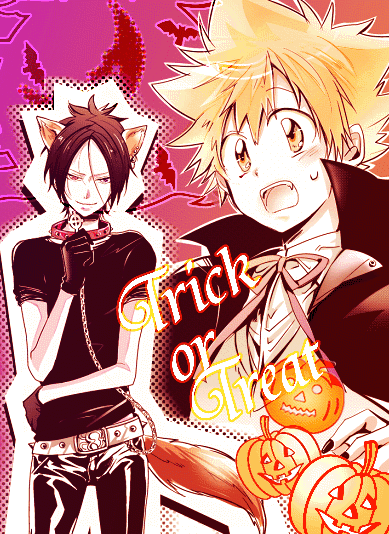
オオカミ骸やらうさツナやら、

お兄さんネタやら

あったはずなのですが 文章がどこかにいっていたりイラストがどこ保存してあるんだ〜〜〜〜で行方不明だったりで(・▽・;)一部、欠けております…。読みたいモノがないぞー!!だったらすみません;;総投稿数が、50件くらいになっていたような! ともあれお付き合いくださった皆様、萌えの発散にお付き合いいただいた新さん(あらたさんのイラストをみたいがために書いたフシが大量にありましたとも…!!←) 長らくありがとうございました〜!!!><*
ちなみにこんなアイコンも作ってもらえたりして


しあわせ…でした…幸せきわまりなかったです。ありがとうございました…!!